1989年
1989年
カルフール・ヴァヴァン(エコール・ド・パリの芸術家たちのプロモーションを目的とした文化協会)で開催された展覧会
展覧会タイトル:《ズボロフスキー、肖像と風景》
主催:カルフール・ヴァヴァン
場所:パリ第6区区役所
出展作家:モディリアーニ、スーティン、キスリング、アンチェール、エビッシュ
展覧会監修
マルク・レステリー二の画商ズボロフスキーに関する大学論文にもとづいた展覧会
1990年
1990年
《ヨーロッパの巨匠(1870年〜1970年)初期の名品》展
場所:パリ、ジャックマール・アンドレ美術館、
ストラスブール、日本、スペインに巡回
1991年
1991年
現代画家フロール (Flaure)の展覧会
場所:パリ、リュクサンブール美術館
展覧会監修
1992年
1992年 
《モディリアーニ》展
東京、東武美術館の開館記念展
展覧会監修
1993年
1993年

《ルノワール》展
主催:毎日新聞社
場所:東京、東武美術館、大阪市立美術館(1993年7月)
展覧会監修
1993−94年

《モディリアーニと仲間たち》展
日本国内を巡回
展覧会監修
1994年
1994年 
《ズボロフスキーと画家−モディリアーニ、ユトリロ、スーティンと仲間たち》展
スイス、ローザンヌ、エルミタージュ美術館の10周年記念展
展覧会監修

《アンドレ・ドレン、近代的混乱の画家》展
パリ市近代美術館での展覧会に協力

上掲、《ズボロフスキーと画家−モディリアーニ、ユトリロ、スーティンと仲間たち》展
場所:イタリア、フィレンツェ、ヴェッキオ宮殿に

《スーティン》展
場所:スイス、ルガーノ市立近代美術館
展覧会協力
1995年
1995年

《女流印象派》展
東京、伊勢丹美術館
展覧会監修
《アンドレ・ドラン》展
マドリード、ティッセン・ボルネミッサ美術館
展覧会協力
1996年
1996年

《ブーダン》展
日本初の巡回展
展覧会監修
《永遠の女性》展
ドイツ、バリンゲン、スタッドハーレ美術館
展覧会協力
1997年
1997年

《ジョルジュ・ルオー》展
スイス、ルガーノ市立近代美術館
展覧会監修

《モディリアーニとスーティン》展
日本での巡回展
展覧会監修
1998年
1998年
 《ウジェーヌ・ブーダン(1824-1898) – 印象派の先駆者》展
《ウジェーヌ・ブーダン(1824-1898) – 印象派の先駆者》展
没後100年記念展
コロンビア、ボゴタ、国立美術館
展覧会監修

《キキ、モンパルナスの女王》展
日本での巡回展
展覧会監修

《ルオー》展
安田火災東郷青児美術館ほか
展覧会監修
1999年
1999年
 《ロー・コレクション、西洋絵画の500年》展
《ロー・コレクション、西洋絵画の500年》展
東京、安田火災東郷青児美術館ほか
その後、米国、ヨーロッパを巡回
展覧会監修

《パリ市近代美術館》展
日本で巡回
コーディネーター
展覧会監修:シュザンヌ・パジェ
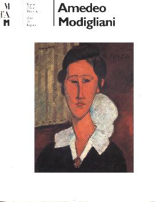
《モディリアーニ》展
スイス、ルガーノ市立近代美術館
展覧会監修
2000年
2000年

《シスレー》展
東京、伊勢丹美術館ほか
展覧会監修
 キリスト生誕2000年記念《モネ−光の巨匠》展
キリスト生誕2000年記念《モネ−光の巨匠》展
ローマ、リゾルジメント美術館
展覧会監修

《ピカソ》展
コロンビア、ボゴタ、国立美術館
展覧会監修

《フラ・アンジェリコからボナールまで:ロー・コレクション名品》展
展覧会監修
パリ、リュクサンブール美術館の再整備記念展
リュクサンブール美術館長就任
2001年
2001年

《オディロン・ルドン》展
日本での巡回展
展覧会監修
 《1900年のロダン、アルマ》展
《1900年のロダン、アルマ》展
リュクサンブール美術館
1900年パリ万博の時にアルマ広場に設置されたロダン館で開催されたロダンの石膏作品による展覧会の復活。国立美術館連合およびパリのロダン美術館との協力により実現した展覧会。

《モネ》展
山口きらら博に際して山口県立美術館で開催された展覧会
展覧会共同監修

《ラファエロ》展
パリ、リュクサンブール美術館
世界中から集めたこれまで門外不出の作品を多数含む13点によるウルビノの巨匠の初の回顧展。イタリア文化省およびヴァティカンとの協力により実現。
2002年
2002年

《クールベ》展
栃木県立美術館創立30周年記念展
オルナン市のクールベ美術館から出展
展覧会監修:ジャン=ジャック・フェルニエ

《ロー・コレクション》展
イタリア、ベルガモ、アカデミア・カラーレ美術館

《ロー・コレクション》展
コロンビア、ボゴタ、国立美術館
2002 – 2003年

《モディリアーニ、深刻な顔の天使》展
パリ、リュクサンブール美術館
油彩110点が出展されたモディリアーニの過去最大規模の展覧会
展覧会監修
2003年
2003年

《モディリアーニ》展
イタリア、ミラノ、パラッツォ・レアーレ
1958年に同美術館で開催されたリオネッロ・ヴェントゥーリ監修で開催された展覧会
依頼のモディリアーニ展
ジャンヌ・エビュテルヌの油彩、素描が初めて出展された展覧会
パリの《モディリアーニ》展よりも素描家としてのモディリアーニの側面が掘り下げられた展覧会

《ゴーギャンとポン・タヴァン派の冒険》展
リュクサンブール美術館
ポン・タヴァンにおけるゴーギャンの初期の作品を紹介した初の展覧会
2003−2004年
ピナコテーク・ド・パリ開館
文化大臣臨席
質の高い展覧会の開催を目的としたフランス初の私立美術館

ジャクリーヌ・コレクションによる
《ピカソ》展
ピナコテーク・ド・パリの開館展
2004年
2003−2004年
《アフリカ大陸の至宝》展
イタリア、トリノ、近代美術館
西暦紀元1000年代から20世紀初頭までの名品
(一大陸の歴史的、文化的、芸術的な遺産)の総合展示
展覧会協力
2004 – 2005年
《ピカソ》展
1年間日本国内の主要美術館を巡回
2005年
2005年
《アフリカの芸術》展
モナコ、ガリマルディ・フォーラム
アフリカ大陸の心と芸術へ誘う旅のような体験ができる展覧会
展覧会協力
2007年
2007年
マドレーヌ広場でピナコテーク・ド・パリが開館

《ロイ・リキテンスタイン:進化》展
ピナコテーク・ド・パリ
ピナコテーク・ド・パリのマドレーヌ広場での開館記念展
《ヴェネツィア絵画のきらめき》展
豊田市美術館、静岡県立美術館、大分市美術館、Bunkamuraザ・ミュージアム、鳥取県立博物館を巡回
展覧会監修

《モディリアーニと妻ジャンヌの物語》展
Bunkamuraザ・ミュージアム、札幌芸術の森美術館、大丸ミュージアム・梅田、島根県立美術館、山口県立美術館を巡回
2008年
2008年

《シャイム・スーティン》展
ピナコテーク・ド・パリ

《マンレイのアトリエ》展
ピナコテーク・ド・パリ

《永遠の兵士たち》展
ピナコテーク・ド・パリでの兵馬俑展

《モディリアーニ》展
東京、国立新美術館
大阪、国立国際美術館
展覧会監修
《アメデオ・モディリアーニとジャンヌ・エビュテルヌ》展
韓国、ゴーヤン市立アラム美術館
展覧会監修

《ポロックとシャーマニズム》展
ピナコテーク・ド・パリ
2009年
2009年

《ヴァラドンとユトリロ –モンマルトルの変換期−印象派からエコール・ド・パリ》展
ピナコテーク・ド・パリ

《オランダ黄金時代—レンブラントからフェルメールへ》展
ピナコテーク・ド・パリ
2010年
2010年

《エドワルド・ムンクあるいは「叫びではなく」》展
ピナコテーク・ド・パリ
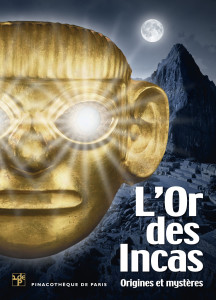
《インカの黄金—始まりと神秘》展
ピナコテーク・ド・パリ
2011年
2011年
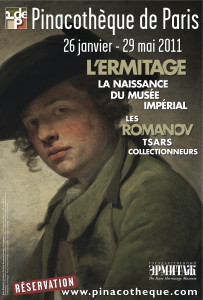
《エルミタージュ美術館、ロマノフ朝の美術館、ツァーリのコレクション》展
ピナコテーク・ド・パリ

《美術館の誕生−エステルハージ家、王子のコレクション》展
ピナコテーク・ド・パリ

《ユーゴ・プラットの空想旅行》展
ピナコテーク・ド・パリ

《ジャコメッティとエトルリア美術》展
ピナコテーク・ド・パリ

《ドイツ表現主義—青騎士からブリュッケ、ベルリン−ミュンヘン、1905-1920》展
ピナコテーク・ド・パリ

《イローネ&ジョルジュ、クレメール夫妻コレクション、オランダ黄金時代の遺産》展
ピナコテーク・ド・パリ
2012年
2012年

《マヤ文明、翡翠の仮面》展
ピナコテーク・ド・パリ

《ネテール・コレクション、モディリアーニ、スーティンとモンパルナスの冒険》展
ピナコテーク・ド・パリ

《ヴァン・ゴッホ、日本の夢》展
ピナコテーク・ド・パリ
《広重、旅の芸術》展
ピナコテーク・ド・パリ
2013年
2013年
《ネテール・コレクション、モディリアーニ、スーティン、呪われた画家たち》展
イタリア、ミラノ、パラッツォ・レア−レ、
ローマ、パラッツォ・チッポラ

《アール・ヌーヴォー、装飾の革命》展
ピナコテーク・ド・パリ
《タマラ・ド・レンピッカ、アール・デコの女王》展
ピナコテーク・ド・パリ
《アート・コレクション》展
シンガポール、ピナコテーク・ド・パリにおけるポップ・アップ展

《時代の証人としての画家たち》展
• ゴヤと近代
• ブリューゲル・ファミリー
• シュ・テ=シュン(朱徳群)、抽象への道
ピナコテーク・ド・パリ

《エドワルド・ムンク》展
イタリア、ジェノヴァ、パラッツォ・ドゥカーレ
2014年
2014年

《クレオパトラ神話》展
ピナコテーク・ド・パリ
 《カーマ・スートラ− インド芸術における性と精神性》展
《カーマ・スートラ− インド芸術における性と精神性》展
ピナコテーク・ド・パリ

《愛の芸術−名作秘画、歌麿から北斎、広重まで》展
ピナコテーク・ド・パリ
2015年
2015年

《クリムトの時代−ウィーン分離派》展
ピナコテーク・ド・パリ

《プレッショニスム、グラフィティ・アートの名作、バスキアからバンドーまで, 1970-1990》展
ピナコテーク・ド・パリ
展覧会監修:アラン=ドミニク・ガリシア
《クレオパトラ神話》展
シンガポール、ピナコテーク・ド・パリ美術館の開館展

《リューベンスからヴァン・ダイク、ゲルステンマイヤー・コレクションのフランドル絵画の名作》展
ピナコテーク・ド・パリ
2016年
2016年

《レオナルド・ダヴィンチ、天才》展
アトランティコ手稿の秘密
ピナコテーク・ド・パリ

《カール・ラガーフェルドの写真、視覚の旅》展
ピナコテーク・ド・パリ
2017
2017
 MODIGLIANI, SOUTINE ET AUTRES LÉGENDES DE MONTPARNASSE au Musée Fabergé de Saint-Petersbourg (Russie). Commissaire
MODIGLIANI, SOUTINE ET AUTRES LÉGENDES DE MONTPARNASSE au Musée Fabergé de Saint-Petersbourg (Russie). Commissaire
***
美術や美術史あるいは美術館に関心のある人にとってマルク・レステリーニはフランスの美術界におけるシンボル的な存在です。モディリアーニの最高権威のひとりでありピナコテーク・ド・パリ美術館の創設者でもあるマルク・レステリーニの業績により、展覧会の実現方法と作品の展示方法は根本的に大きく変革されました。多くの人々の注目を集める彼の輝かしい業績のいくつかをご紹介します。
マルク・レステリーニにとって展覧会はもっとも好ましい表現方法でした。彼は教育普及と専門性がバランスよく融合した特別な展覧会を構想し、人々の記憶に残る展覧会を数多く実現しましたが、その中には例外的なほどの大成功を収めたものもあります。この20年間で開催された最も動員の多かった10の展覧会のうち少なくとも5つはマルク・レステリーニによって実現されたものです。
彼はそれらの展覧会により大衆の作品の感じ方や作品の解釈の仕方を180度変換しました。彼がこの世界でのキャリアを開始した頃は、美術館の世界はそれまで30年、40年と続いてきた、作品は赤色の壁に10cmにも満たない感覚で床から天井までびっしり掛けるものだという《古いい美術館》体質の変革の最中でした。アンドレ・マルローの時代に推し進められたこの変革はそれまでとは正反対の方向に改められ、作品は白い壁に冷たい照明のもと10mも間隔をあけて展示されるようになりました。この冷たい展示は時に作品そのものを損なうほどにもなっていました。このようなやり方は作品の鑑賞を極度に疎外し、流行の美意識で作品をまったく台無しにし、作品を知的な面だけでしか見ないという状況になっていました。
マルク・レステリーニはこの白い壁を極度に嫌い、色のついた展示壁を復活させることによって作品の展示方法に建築的要素を導入しました。また、照明を改善し、作品ごとの照明を工夫することによって、作品の鑑賞に再び新たな感動をもたらしました。作品同士の対話という観点から作品同士の間隔を狭めることと、作品の鑑賞者が美術史の基礎(なかでも図像学と比較科学)を理解できるような教育的観点を導入することが彼のアプローチの中心でした。そして、彼はひとつの展覧会の中で文化と文明を接近させることを可能にする領域横断というコンセプトを表明することになりました。
これまでの規準を根本的に考え直すこのようなアプローチによりマルク・レステリー二は展示作品の素晴らしさだけでなく、そこで紹介された芸術家たちの作品のまったく新しい解釈によって今も記憶に残る真にインパクトのある展覧会を実現しました。
そして、リュクサンブール美術館で開催された《Modigliani, l’Ange au Visage grave》(モディリアーニ,深刻な顔の天使)展はこのイタリア人画家の作品の完全な再解釈を提示した展覧会として有名です。規模の点でもタブロー110点、素描40点と過去のモディリアーニ展の中でも最大のものでした。この大胆な試みの展覧会は一般大衆の関心を集め60万人以上の動員を記録し、同時期にグラン・パレで開催された《Picasso-Matisse》(ピカソとマティス)展の動員を上回りました。
また、同時開催された《Van Gogh, Rêve de Japon》(ヴァン・ゴッホ、日本の夢) 展と
《Hiroshige, l’art du voyage》(広重、旅の芸術) 展によるヴァン・ゴッホの再解釈も注目されました。この展覧会ではヴァン・ゴッホと18〜19世紀の浮世絵芸術との強迫観念に駆られた関係が明らかにされました。この展覧会5ヶ月の会期中に80万人以上の入場者があり、ピナコテーク・ド・パリの最多入場者記録となりました。
領域横断というコンセプトの適用と芸術家の再評価という観点は今日でも高く評価されている《Pollock et le Chamanisme》(ポロックとシャーマニスム)展や《Giacometti et les Étrusquesジャコメッティとエトルリア彫刻》展に強く反映されています。前者ではポロックを初めてプリミティブ・アートとアメリカインディアンとの関係において捉え直し、後者では初めて今まで推論でしかなかった両者の関係の歴史的、科学的証拠を呈示しました。
秦の始皇帝の墓稜より発掘された兵馬俑をフランスで初めて展覧して成功を収めた《Guerriers de l’éternité》(永遠の兵士たち)展、100点もの作品を集めてこれまで開催された中では最も重要な《Soutine》(スーティン)展、またアムステルダムの国立美術館の協力により実現した《L’Âge d’Or Hollandais》(黄金時代のオランダ)展は60万人以上の入場者数で大成功となりました。
これらの大展覧会は多くの話題を提供し論争を巻き起こしました(それらは公的な文化機関からの嫉妬の的にもなりました)。そしてパリの、フランスの展覧会の業界を継続的に変革していきました。今日、展覧会のテーマだけでなく展示方法、教育的アプローチにおいて、ピナコテーク・ド・パリとマルク・レステリーニの業績からの教示に直接的間接の影響を受けていない展覧会はないと言っても過言ではないでしょう。
エリアント・ブルドー=モラン
美術館世界の著名人「マルク・レステリー二」
エリアント・ブルドー=モランの記事からの抜粋(Storify誌、2017年2月号)


